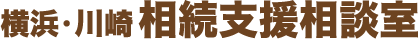教育資金の一括贈与とは?節税効果がある?
我が国の政策上、高齢世代に滞留した資産を消費意欲が活発な若年世代に移転しやすい環境づくりが進められています。
税施策上も色々な特例などが整備されていますが、贈与の分野ではその一つに教育資金の一括贈与の非課税特例というものがあります。
本章ではこの特例がどういうものか解説していきます。
1500万円までの贈与が非課税になる
一定の教育資金を贈与した場合、1500万円までが非課税扱いとなり贈与税がかからなないのが本特例です。
対象者となれる者のうち、贈与者となるのは祖父母や親などの直系尊属です。
受贈者となるのは直系尊属の子や孫、ひ孫などの下の世代です。
ただし受贈者となる側は30歳未満でなければならないという年齢制限が付いています。
ポイントは教育資金という使途を限定した運用であること、贈与税の非課税枠(年110万円)を超える大きな財産を無税で贈与できる点です。
ただし「教育資金」の考え方が少し難しく分かりにくいため注意を要します。
塾や習い事の資金は制限がある
本特例でいうところの「教育資金」は中身が少し複雑なため注意を要します。
まず、教育資金は
①「学校等に対して直接支払われるもの」
②「学校等以外に対して直接支払われるもの」
の大きく二つに分かれます。
①はさらに
a入学金、授業料、施設設備費、入学試験の費用など
b学用品の購入費用、修学旅行費や学校給食費など
に分かれます。
②は例えば塾や音楽、スポーツなどの習い事にかかる費用で、その役務提供者や指導者に直接支払うものです。
塾などを中心とした上記の②については合わせて500万円までという制限が付いているので注意してください。
なお少しややこしくなりますが、②には①のうち、学校等が必要と認めたbに関する費用も含まれます。
②はこれらを合わせて500万円までということです。
暦年贈与と併用できる
教育資金の一括贈与の特例は贈与税の基礎控除(年間110万円まで)と併用することができます。
相続時精算課税制度の場合は一度利用してしまうと暦年課税制度には戻れないので基礎控除枠がなくなってしまいますが、本特例はそうした心配は不要です。
教育資金とは別に、年間110万円までであれば贈与をしても贈与税がかかりません。
本特例に詳しい税理士であれば、この仕組みを活用して節税作用を引き出すことができます。
ただし、本特例にはデメリットとなる落とし穴もいくつかあるので、専門家に相談せずに利用するのは危険が伴います。
利用する場合の手続きの方法は?
教育資金の一括贈与の特例を利用するには贈与者、受贈者の他に、実際に教育資金を払い込む金融機関とも連携する必要があります。
まず贈与者と受贈者の間で贈与契約を結びます。
次に、受贈者は資金を管理する金融機関と教育資金管理契約を結びます。
金融機関に教育資金を払い込んだ後、受贈者の住所地を管轄する税務署に「教育資金非課税申告書」を提出します。
ここまでは本特例を適用する手続きですが、実際に教育費を金融機関から引き出す手続きは2つの方法があります。
一つは、教育費を支払った受贈者がその領収書などを都度金融機関に提出して、当該額の支払いを受ける方法です。
もう一つは先に必要な資金を引き出しておいて、教育資金を支払った後で一定時期までに金融機関に領収書等を提出する方法です。
どちらも各金融機関によって取扱いが異なるので確認が必要です。
落とし穴も!?使いきれなかった分に課税される可能性がある
本特例を利用して教育資金を払い込んだ後、その資金を使いきれなかった場合はその時の状況によって扱いが変わります。
受贈者が30歳に達した時点で贈与者も受贈者も生存していた場合、残った資金には基礎控除110万円を超えている分に贈与税が課税されます。
受贈者が30歳に達する前に贈与者が死亡した場合には贈与者の相続財産とはならず、受贈者が30歳に達した時点でなお残っている分が贈与税の課税対象になります。
この場合、相続前3年以内の贈与にかかる相続財産への加算はしなくても大丈夫です。
契約途中で受贈者が死亡した場合にはその時点で契約は終了となり、残った資金は受贈者の相続財産として扱われることになります。
教育資金の一括贈与のことなら当事務所にご相談ください
今回は贈与税にかかる教育資金の一括贈与の特例について基本的なところを見てきました。
特徴として一括で多額の資金を贈与できるものですが、本特例があなたにとって有利になるかどうかは具体的に検討してみないとはっきりさせることはできません。
というのも、元々扶養義務の範囲内の贈与は非課税とされているので、無理をして一括贈与をすることに有利性を見出すことができる例はあまり多くないのです。
利用するにしても、教育資金の中身の扱いが難しく、思っていたように利用することができなかったという事例もよく聞きます。
利用にあたっては落とし穴にはまらないよう、専門家に相談しながら検討することが大切です。