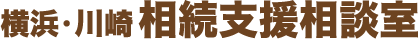非課税で2500万円も贈与可能?相続時精算課税制度のメリットと注意点
我が国の税制度は他国に比べても複雑で分かりづらいとよく言われますが、一般の方にはスッキリとした理解がなかなか難しい複雑な内容の法律や運用方法を用いていること、また特例や例外などが多数あることなどが要因と考えられます。
相続税分野においては特にこれが顕著で、皆さんが感じる「とっつきにくさ」につながっているわけです。
同分野で特に分かりづらいと言われるのが「相続時精算課税制度」ですが、今回はこの制度がどのようなものなのか解説していきます。
贈与税が2500万円までかからない
通常、財産を贈与した場合、年110万円までの基礎控除を超える部分については贈与税を課税されてしまうところ、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までは贈与税が課税されません。
高齢世代から消費意欲の高い若年世代への財産の移転を容易にし、消費活動を促進して国の経済に貢献させようというのが本施策の目的となります。
2500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課されますが、この税率も本来の贈与税率に比べればかなり有利なものとなっています。
贈与税を負担せずに多額の財産移転が可能
「子や孫に援助してやりたいが、贈与税がネックだな」という場合に本制度の強みが発揮されます。
多額の財産を一度、あるいは複数回に分けて贈与しても贈与税がかからないので、ケースによっては大きなメリットを生みます。
贈与税の基礎控除の枠を超えた贈与の必要性が強い場合の利用が考えられます。
ただし、本制度は贈与財産に対しての課税の免除ではないことには要注意です。
課税免除ではなく課税の「先延ばし」であることに注意
大きな財産移転を贈与税の負担なく行える点でメリットがありますが、その財産については課税が完全に免除されたわけではありません。
贈与された財産は、贈与者に相続が発生した時、相続財産に組戻して計算しなければなりません。
本施策の名称は「相続時精算課税制度」ですから、相続時に合わせて課税しますよ、という意味です。
相続時には相続税の基礎控除枠がありますから、組戻し計算をしてもその範囲に収まっていれば税負担が生じませんが、それを超えることになった場合は相続税が課税されてしまうことになります。
ここで、組戻し計算される財産の価額は贈与時のものとなるため、相続時に贈与時よりも財産の価値が上がっていた場合はその差額について節税作用が起きることになります。
逆に値べりしてしまった場合はその分の価値下落分については考慮されないことになります。
暦年贈与の非課税枠が使えなくなる
相続時精算課税制度の利用にあたって絶対に考慮すべきなのが、暦年贈与との併用が不可となっていることです。
どちらか一方しか選択できず、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与に戻ることはできません。
年間110万円までとなっている贈与税の非課税枠は暦年贈与でしか利用できないので、誰にでも使いやすくデメリットも少ない贈与税の非課税枠を使った生前対策ができなくなることは知っておかなければなりません。
その他にも本制度にはいくつかのデメリットがあるので、次の項でまとめて見てみましょう。
相続時精算課税制度のデメリット
この項では暦年贈与に戻れない他に、相続時精算課税制度のデメリットにどんなものがあるのかまとめます。
相続税の課税対象になる
これは先にも述べましたが、相続時には組戻し計算によって相続財産に加えられてしまうため、相続税の基礎控除を超えると税負担が生じることがあります。
贈与と相続全体を通して必ずしも節税効果があるわけではないということは意識しておく必要があります。
小規模宅地の評価減の特例が受けられない
相続時には一定の小規模宅地について大幅に評価を下げて計算することができる小規模宅地の特例があります。
相続で承継する土地については利用できるのですが、生前に贈与を受けた土地についてはこの特例が利用できなくなります。
一定のコストがかかる
相続で土地を取得した場合は不動産取得税がかかりませんが、贈与で取得した場合は一定の不動産取得税が課税されます。
本則は固定資産税評価額の4%となっていますが、土地について平成30年までは3%となっています。
宅地については平成30年まで課税標準が固定資産税評価額の二分の一となります。
また登記の際に必要な登録免許税は相続による取得の場合は課税標準の0.4%となっているところ、贈与による取得では2%となります。
税務署への申告が必須
相続時精算課税制度を利用したい場合、贈与の額の大小に関わらず税務署に申告手続きをすることが義務づけられます。
手続きをしないと同制度の適用がなくなり、贈与財産に贈与税が課税されてしまうので注意してください。
相続時精算課税制度のご相談は当事務所まで
相続時精算課税制度は節税目的で利用しようとすると逆効果になってしまう恐れがあるので、将来の不確実性も考慮した綿密な予測計算が必要になってきます。
当事務所で詳しくお話を聞かせていただきますので、あなたのケースではデメリットを超えるメリットがあるのかを確認することができます。